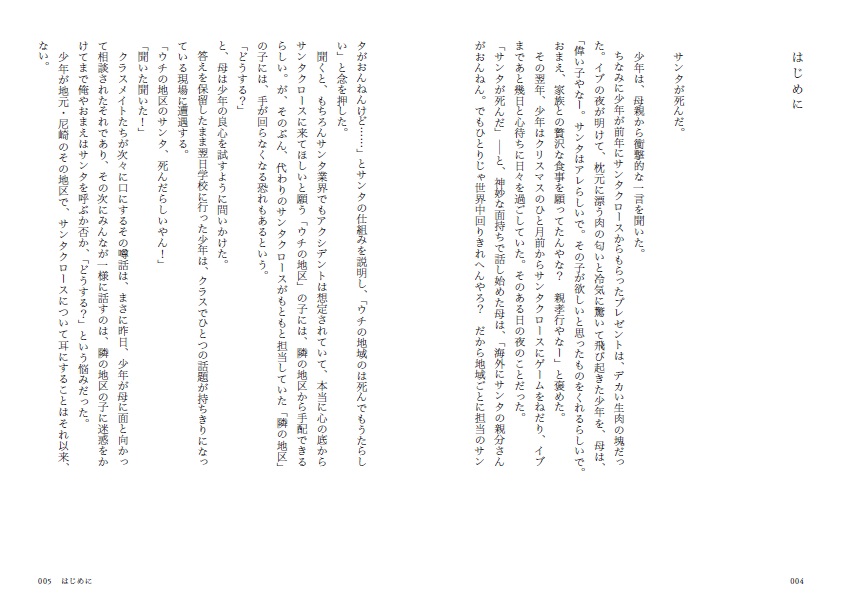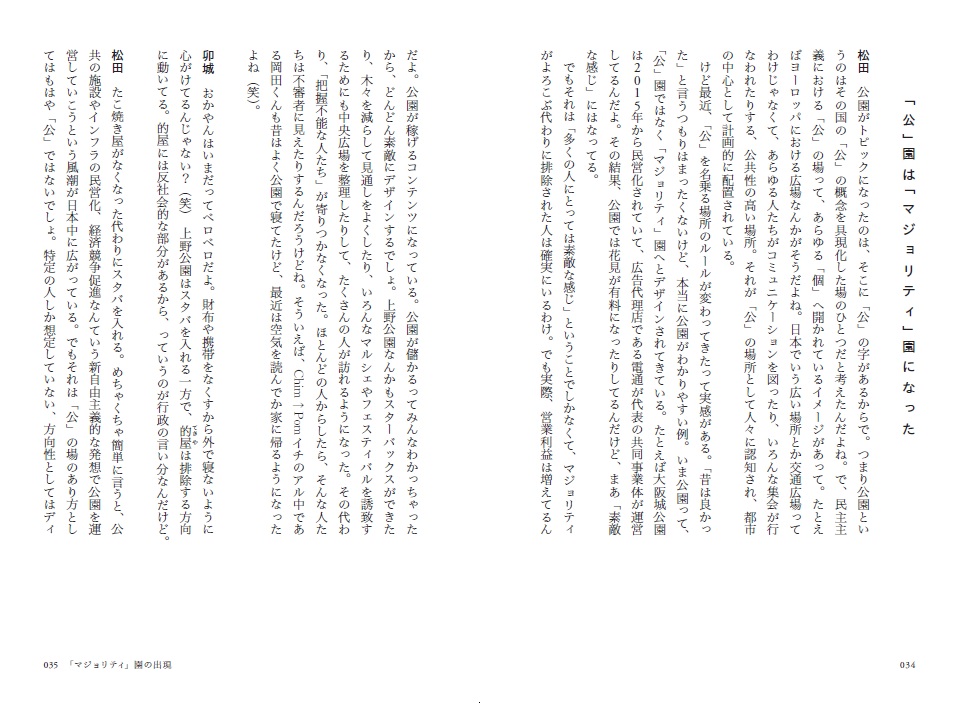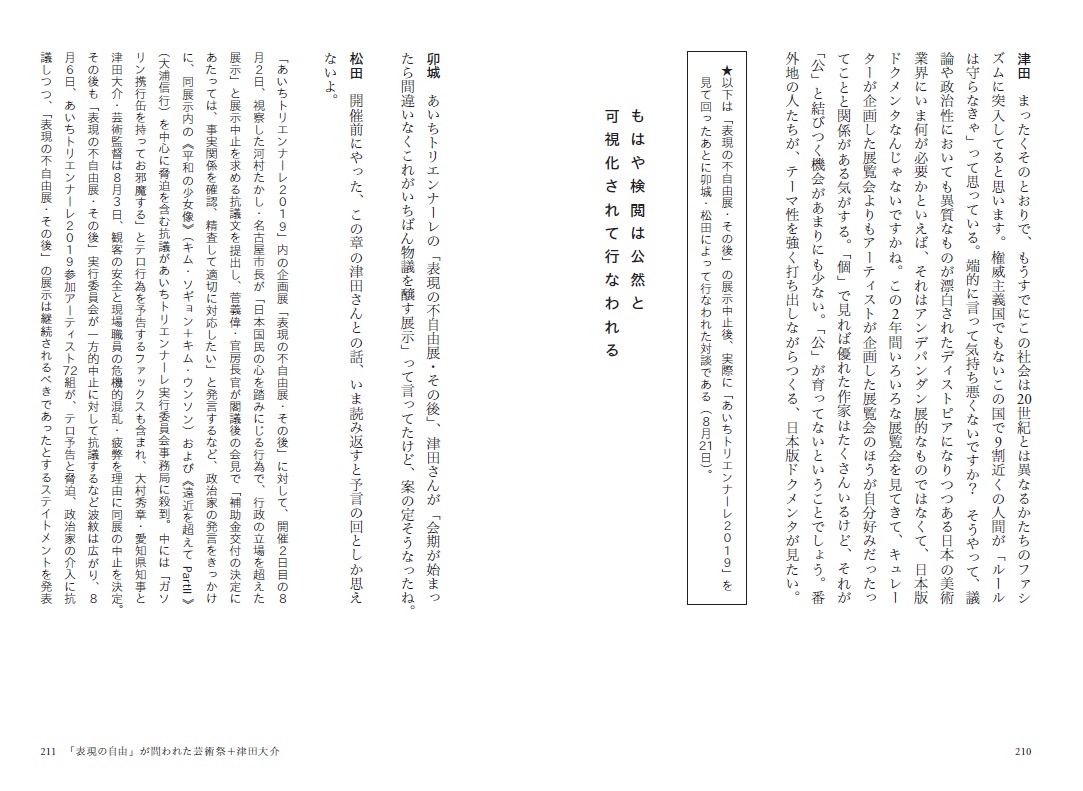はじめに 卯城竜太(Chim↑Pom)
サンタが死んだ。
少年は、母親から衝撃的な一言を聞いた。
ちなみに少年が前年にサンタクロースからもらったプレゼントは、デカい生肉の塊だった。イブの夜が明けて、枕元に漂う肉の匂いと冷気に驚いて飛び起きた少年を、母は、「偉い子やなー。サンタはアレらしいで。その子が欲しいと思ったものをくれるらしいで。おまえ、家族との贅沢な食事を願ってたんやな? 親孝行やなー」と褒めた。
その翌年、少年はクリスマスのひと月前からサンタクロースにゲームをねだり、イブまであと幾日と心待ちに日々を過ごしていた。そのある日の夜のことだった。
「サンタが死んだ」 ――と、神妙な面持ちで話し始めた母は、「海外にサンタの親分さんがおんねん。でもひとりじゃ世界中回りきれへんやろ? だから地域ごとに担当のサンタがおんねんけど……」とサンタの仕組みを説明し、「ウチの地域のは死んでもうたらしい」と念を押した。
聞くと、もちろんサンタ業界でもアクシデントは想定されていて、本当に心の底からサンタクロースに来てほしいと願う「ウチの地区」の子には、隣の地区から手配できるらしい。が、そのぶん、代わりのサンタクロースがもともと担当していた「隣の地区」の子には、手が回らなくなる恐れもあるという。
「どうする?」
と、母は少年の良心を試すように問いかけた。
答えを保留したまま翌日学校に行った少年は、クラスでひとつの話題が持ちきりになっている現場に遭遇する。
「ウチの地区のサンタ、死んだらしいやん!」
「聞いた聞いた!」
クラスメイトたちが次々に口にするその噂話は、まさに昨日、少年が母に面と向かって相談されたそれであり、その次にみんなが一様に話すのは、隣の地区の子に迷惑をかけてまで俺やおまえはサンタを呼ぶか否か、「どうする?」という悩みだった。
少年が地元・尼崎のその地区で、サンタクロースについて耳にすることはそれ以来、ない。
これは本書の共著者、現代美術家・松田修の実体験だ。
日本中にサンタはいる。それはゲトーだった尼崎も同じ。「サンタはいる」という暗黙のルールは、有無を言わさず世界中で共有されている。しかし、松田の家とそのコミュニティはその寓話を編集し、それを地域の「お決まり」にした。大きな物語が改変されて、サンタが死んだことを松田少年は悲しんだろうか。たぶんそうだろう。当時は。けれども、現在の松田はそのことを、悲劇はおろか喜劇というよりもむしろ、自分には世界中の子供たちが体験する冬の夜のメインストリームとは違う独自のクリスマスがあったよと、忘れられない経験として自慢げに話す。それが、いまの彼のアイデンティティのひとつでもある「オルタナティブ」の原風景でもあるかのように、思い出して笑う。
寓話が通じない。いくら日本中、いや世界中に浸透していても――
同じ「お決まり」、同じ慣習に従って、同じ風景へと日本中がどんなにつくり変えられたとしても、はたして「同じこと」だけが全国津々浦々で起きるんだろうか。
いま、戦後最大級の再開発が進む東京は、まるでひとつのコンセプトからデザインされるかのように均一化へと向かっている。全国の国道沿いや駅前の風景が同じだなんて
感想や警鐘も、もう何十年も聞いてきた。だとしても、そうして「公なるもの」による都市論が、その街を歩く「個」のルートやスピードや消費の傾向を一律に設計したとしても、その思惑どおりに多くの個が代替可能な動きをしたとしても、本当に「同じこと」だけが起きるんだろうか。
尼崎の一角で「サンタが死んだ」ニュースは、地元の子供たちにとっては残念だったけれど、僕ら部外者には、「そういえばサンタの物語には結末なんてまだなかった」ことを気づかせて、その前人未到の続編を紡ぐ想像力を与えてくれる。クリスマス特需を目論むCMやデパートや政府の統計や経団連には残念な話だけど、サンタが死んでも松田家の幸せなクリスマスは続いていた。
そう、サンタは殺せる。というか殺してもいい。実際には誰も死んでないし、もっと言えば「サンタを殺しちゃいけない理由」なんて本当のところは、ない。けれど、世の中を包むその大きな冬の物語のもとでは、「個」はプレゼントを選び、みんながみんな、「消費者」と化す。大きな物語をDIYに紡ぎなおすことで、その物語のつくり手にだってなれるのに。
この本はウェブ版「美術手帖」で2018年12月から2019年5月にかけて「The Public Times ――公の時代のアーティスト論」というタイトルで連載した、僕と松田の対談(ときどきは鼎談)をもとに新たな論として更新したものだ。
近年、「個と公」のバランスが大きく変わるなかで、僕らには、アーティストというつくり手として、言いたいことがたくさんあった。対談内にウザいくらい出てくる「個」「アーティスト」「大正」といったいくつかのキーワードのうち、とくに「公」の使い方は、論として開始当時はガバガバだ。いまから見るとツッコミどころ満載だが、なぜ僕らがそれほどまでに幅広くいろんな集団や容れ物を「公」と呼びたかったのか。それがいったい何を示唆しているのか、だんだんとわかるようになってきたのは、僕らが自らを「私」ではなく、「個」として捉えることにこだわりを持っていると気づいてからだった。アーティストは、「私」(プライベート)という、「公共」と離れた領域に存在する「私人」ではなく、集団の中でこそ存在しうる「個」(インディビジュアル)の究極形なのだ。公共的な場はもちろん、業界やチーム、家庭など、あらゆる集合体を揺るがすのは「私」ではなく、「個」そのものの力だ。同様に、アーティスト活動に「プライベート」なんてものはない。そうして「個」へのこだわりを話し合っているうちに、僕らはあらゆる集団の中に、「個」の力が試されるべき「公」性とも言うべき性質を見いだしていった。
連載は3回で終わる予定が、蓋を開けてみたら全9回。さらに書籍化のために大改造。そこまで話が膨らんで僕らを悩ませた要因は、この間にも次々と続発した、アートと社会をめぐるアクシデントだった。公的な検閲、作家やキュレーターの自主規制、一般を巻き込んだ炎上は枚挙にいとまがなく、議論を呼ぶアーティストはネット上で「アート無罪」と茶化されて、世界を騒がせる責任の所在を突きつけられていた。時代という浮き世の変化を超越する「個」として、これまで「アーティスト」は歴史的な文脈を紡いできた。そんなリテラシーが議題に上がらないアクシデントの数々を見て、僕はこう思ったのだ。
(アーティストは死滅するだろうな、ある意味)
僕はなんとなく、僕らが戦後民主主義社会の中でイメージしてきた「アーティスト像」の崩壊を感じていた。「個のエクストリームな振り幅」をつくれる存在であるところの「アーティスト」。イデアとしての、イコンとしての、寓話の登場人物のように、お馴染みでありながらも突飛な存在。そんな「アーティスト像」を、社会が「公の時代」と引き換えに追い立てていた。
これはまず僕らアート従事者の話でもあるけれど、「アーティスト」を失う、この社会のリスクの話でもある。炭鉱の最前線で、有毒ガスに敏感なカナリアが危険察知のために持ち込まれていたことから、「アーティストは炭鉱のカナリア」だと、その前衛性はよくたとえられてきた。いまや炭鉱の時代は過ぎて、カナリアはペットとして愛されているが、しかし、そんないまの日本社会そのものに、僕は以前よりも多くの危険を察知するようになった。「公」という大きな物語の中で、「エクストリームな個」が消失した次は、「個」が消える番だ。
サンタを殺したゲトーの話は僕に、たとえ大きな物語の中にいても、誰もがエキストラではなくつくり手になれる可能性を感じさせた。けれども同時に、「一年に一度しか働かない」ような、妙なキャラが消えることの喪失感をももたらした。それを悲観するか、楽観するか、どちらにせよポスト・アーティストの時代は到来している。
「サンタはいまもどっかにおるらしいけどな」
その昔、尼崎で松田少年の母はそう断りを入れて、「けどウチはもう他とはちゃうようになってもうたからなー」と残念がったらしい。けれどもその後、その地域では、「サンタの死後」という新たなクリスマスの物語が始まったのである。