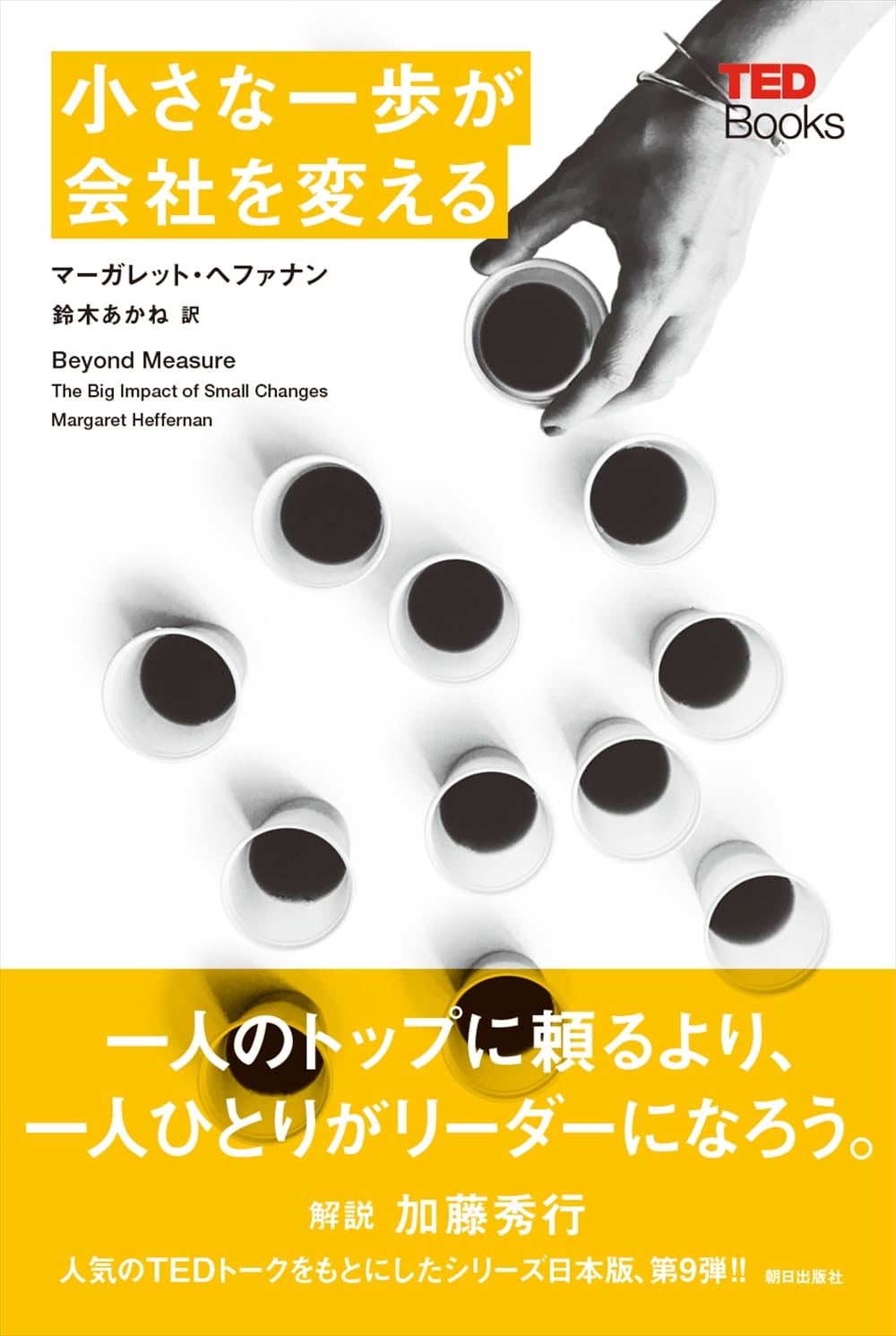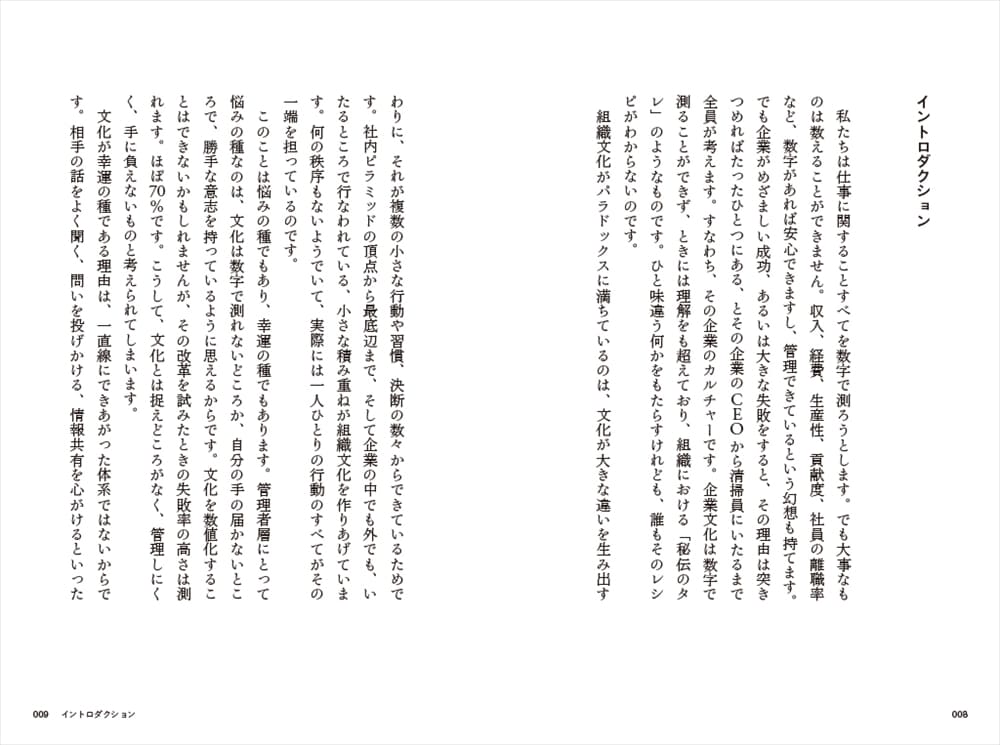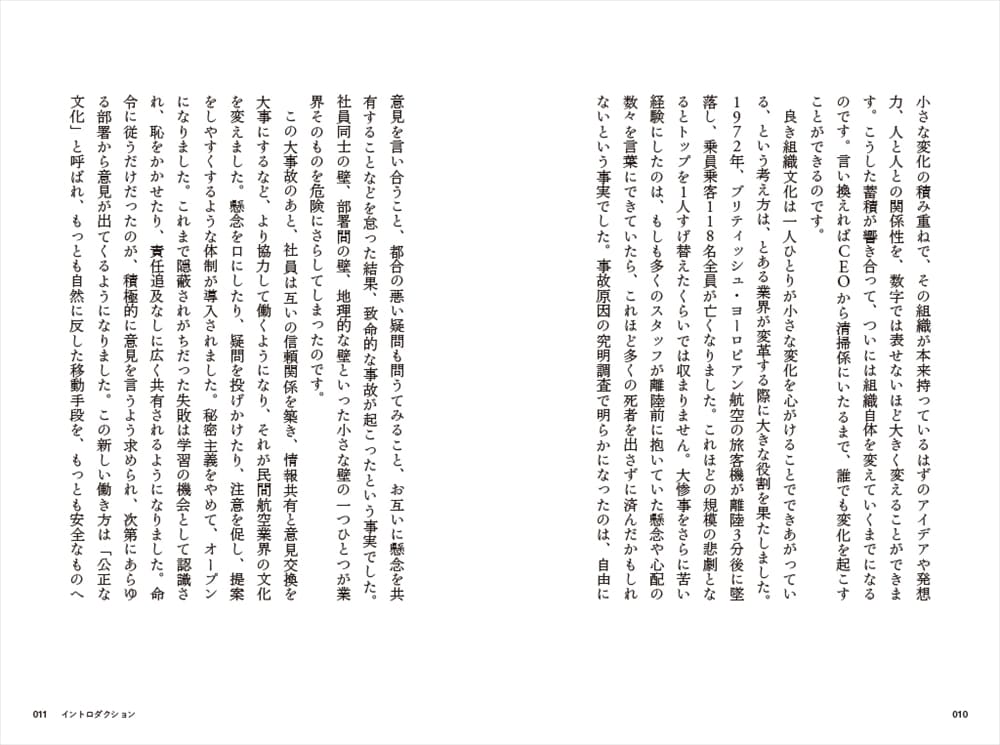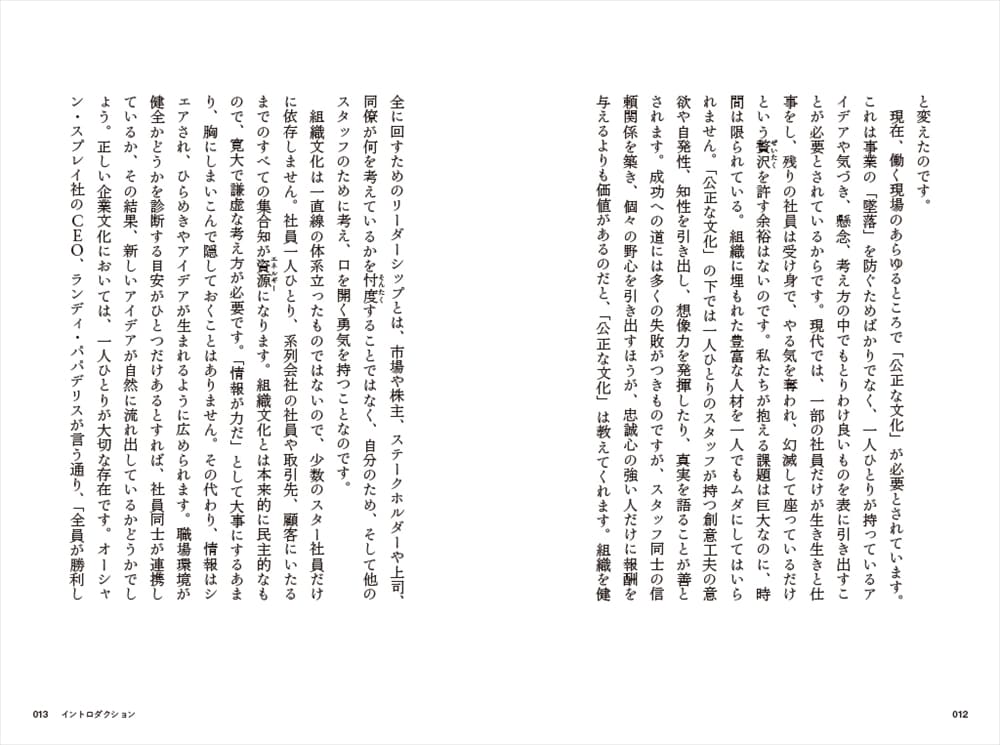小さな一歩が会社を変える
小さな一歩が会社を変える
マーガレット・ヘファナン 著 / 鈴木あかね 訳
定価: 1,925円(本体1,750円+税)
在庫: 在庫あり
電子版を購入する
オンライン書店で購入する
一人のトップに頼るより、一人ひとりがリーダーになろう。
会社を変えるのは「公正な文化」。まずは小さな一歩を踏み出そう。部署を超えて衝突覚悟で意見を言い合う。コーヒーブレイクを社内で一斉に取る。「静かな時間」で一人の作業に集中する。オフィスを飛び出て人や家族と話す。ほんの小さな変化が、劇的な効果をもたらす。組織は創造的に利益を生み出し、仕事の満足度も上がる。数値に表せない、そんなアイデアこそがリーダーだ。世界中の企業を見てきた起業家が、成功と失敗の豊富なケーススタディをもとに、組織と個人との風通しの良い関係を探る。
Small books, big ideas. 未来のビジョンを語る。
人気のTEDトークをもとにした「TEDブックス」シリーズ日本版、第9弾。
本書の著者、マーガレット・ヘファナンのTEDトークは以下のTEDウェブサイトで見ることができます。
www.TED.com(日本語字幕あり)
「失われたチャンスについて一人ひとりに話を聞いても、全員が同じことを言います。『うちの文化が悪いんだ』と。〔…〕では、どうしたらこれを解決できるのでしょう? みんなで、としか言えません。だからこそ本書はCEOから清掃員まで、働きやすい職場を望む、すべての人に向けて書かれています。この本は毎日の思考や習慣の小さな積み重ね、たとえば話し方や聞き方、議論の仕方、考え方、物の見方といったことがカルチャーを生み出し、定着させていくということに着目します。数百万ドルかけて何年がかりにもなる社内改革プランではありません。誰でも、いつでも踏み出せる小さな一歩であり、大きな変化のきっかけとなるほんの小さな一歩を紹介しています」(本書より)
【解説】資本という名の連結電車 加藤秀行
我々は数値を信じやすい。何であれ堅い事実であると思いがちだ。もちろんそれぞれの性質に因る所も大きいけれど、人は数値で表されたことには何らかの真実性が担保されていると感じ易いものだと思う。
だからそれが間違っていたり、意図的に改ざんされていたりすると、なんだかとても憤るのである。牛乳の消費期限が貼り直されていたり、有価証券報告書における重要子会社株式の評価額が明らかに過当評価だったり、γ-GTPが高すぎてビールが思う存分に飲めなかったり(それは、まあ、自己責任だが)、そういうことに対してはとても憤りを覚える傾向にある。
一方で、数値以外で表現された事柄は、どこか曖昧な部分があると本能的に感じている。誰が聞いても一意に定まるようにピタリと表現することなんか本当はできないんじゃないか。そういう諦めが(きっと)どこかにある。
だから「皆様のために必死で公約を守って参ります!」と叫ぶ国政だかの立候補者が公約を守れなくても誰も死にゃあしないし、地方の国道を走っていて道端の古びた店の看板に「日本一! 美味いら〜めん」とか書かれても「まあまあ、そういうのもいいじゃないか」と思うのだ(正確に言うと一番と言ってるから数値だけど、この場合は定量ではなく概念だ)。誰も本気で怒ったりしない。それが我々の基本的な態度だ。
では、数値にも言葉にもなる前のものごとについて、我々の基本的な態度とはどのようなものなのだろうか?
著者は「どうすれば人は組織にもっと貢献したくなるか」という問いを本書の中心に置いている。原題は「Beyond Measure」。企業は数値で測定できないような個人個人の小さな一歩の積み重ねでできており、組織を構成する最小単位である人の、数値では(あるいは言葉でも)表せない側面にちゃんと目を配ることで素晴らしい組織文化を育んで貢献を促進できると、豊富なコンサルティング経験、事例をベースに語っている。
組織に属する。同僚ができる。誰しもできれば何かに貢献したいと思っており、その潜在的な力を最大限引き出すことで、組織の潜在力を最大限引き出すことができる。
本書の中心的な主張は「ゲゼルシャフト(利益社会)的なものを本当にワークさせようとすると、ゲマインシャフト(共同社会)的要素がまぶされていると、より貢献を引き出せる」と言える。
すべてはバランスの中に位置している。
極端にゲゼルシャフト的な環境下で生き延び続けられる人は全体から見ると変わった/偏った一握りの人たちだけだ。数値がおやつで結果がごはん、みたいな人ばかり集まる場所は、世界の大都市の片隅(いや、中心か)に確実に存在している。
一方で、企業全体がゲマインシャフト的方向に振り切りすぎることは許されない。企業には固有のバーンレート(資本燃焼率)がある。例えると極寒の外気にさらされる中で、燃やせるたきぎの総量が決まっているようなものだ。一定の目的を達成し続けなければ、その系(システム)は維持できない。
だから企業体とは常にその中間にあって、放っておくとゲゼルシャフト的な方に向かいがちな存在だと僕は思う。極北にはダイヤより硬い数値と、刃のように研ぎ澄まされた言葉が猛烈に渦巻いている。その環境は「ただ在る」ことを賛美する力学体系ではない。
その大きな枠組みの中で個人はどこに/どう在るべきか。
「数値にも言葉にもなる前の、人の気持ちをちゃんと掬い取る」
そのアイデアは、企業体が置かれている環境プレッシャーと逆行するように見える。だがそれは今まさに多くの(数値をおやつにできない)人が渇望しているものでもある。
なぜか?
それは、どこにも成長の約束がなくなりつつ(少なくとも見えなくなりつつ)あるいま、遠い極北を目指せ(さ)ない多くの人が「目に見える誰かの役に立つことで、今ここに在る体験を得る」ことを重視するようになっているからではないかと思う。
こと人に関する限り、数値にも、言葉にもなる前の実存のどこかに人生の真実はあって、それは、自己充足するか、人との繫がりの中で与えたり貰ったりする中で見出だすものなんじゃないか、と思う。
本来、より高次の系との係わりの中で見出されるものじゃないと思うのだ。
それでもなお残る問題はゲゼルシャフトの巨大な連結電車が最終的にどこに向かおうとしているのか、という点だ。網の目のように張り巡らされた線路から自分だけ抜けるなんてできない。すべての電車はどこかで繫がっていて、押され、引っ張られ、速度をどんどん上げている。
すべての人が乗客であり車掌でもある。その行き先は本来僕らのものだ。
人が手段ではなく目的になればいいと思う。
それまでの過渡期として(今が本当に過渡期であるとして)、本書にあるように、人が一定程度の目的になる組織が、ちゃんと栄えてくれればとてもいいな、と思う。
かとう・ひでゆき 1983年鳥取県生まれ。東京大学経済学部卒業後、堀紘一率いる(株)ドリームインキュベータ(DI)に入社。現在は調査子会社DIマーケティングの社長を務め、ベトナム、タイ、インドネシア、東京の四拠点を管轄。
目次
第1章 クリエイティブな対立
第2章 社会資本
第3章 思考は頭だけの作業ではない
第4章 組織の壁を打開する
第5章 リーダーシップはいたるところに
エピローグ 矛盾と不測の事態